「蒲団(青空文庫)」を読んだ。日本近代文学の原罪みたいな小説。明治四十(1907)年九月、雑誌「新小説」に発表。
「肉の人、赤裸々の人間の大胆なる懺悔録」(島村抱月)とか、「作者の心的閲歴または情生活をいつわらず飾らず告白し発表し得られたという態度の真摯さ」(小栗風葉)とか、「今迄自叙体に用いて居た描写の手法を巧に客観の描写に利用して一種清新な作風を見せた」(相馬御影)とか、異口同音にほめあげ、このころの文学賞ともいえる「推讃の辞」を『早稲田文学』(明治四一.二)から得て、面目を施した。
引用は集英社版「日本文学全集7田山花袋」に収録された瀬沼茂樹による「作家と作品」より。
上のような評価は文学史的常識としての「蒲団」評。このうち現代でも有効なのは相馬御影の評だけ。確かに尾崎紅葉の言文一致体などと比べると格段に読みやすい。問題は内容が詰まらないことだ。
何故詰まらないのか。性のモラルがとっくの昔に変わってしまったからだ。なものだから、本作は悲劇なき悲劇になっている。有名なラストシーンも笑うことさえできないほど大人しい。つまり内容が空っぽなのである。
一応あらすじを紹介すると、中年の作家時雄くんのもとに若い女芳子さんからファンレターがくる。文通が始まる。のぼせあがった芳子さん、上京して時雄くんに弟子入りしたいとか言い出す。それにのぼせあがった時雄くん来させてしまう。妻も子もいる時雄くんの家で芳子さん同居。時雄くん幸せいっぱい。「新しい女におなりさい」と芳子さんを煽りまくり。でもそのあと芳子さんは時雄くんの奥さんのお姉さんちに下宿。時雄くん残念な気持ちでいっぱい。
そのうち芳子さんに彼氏ができる。相手は同志社大学の田中くん。芳子さん時雄くんに恋愛相談。時雄くん大人ぶってアドバイス。でも心の中では「芳子さんはもうやっちゃったんだろうか。もうやっちゃったんだろうか」と疑いの気持ちでいっぱい。ヤケ酒とか煽っちゃう。そのうち「やっぱりあの子はハイカラすぎて困る。俺が手元で監視しよう」と芳子さんを家に連れ帰る。段々言うことが説教くさくなってくる。でも芳子さんは彼氏の田中くんと盛り上がり続ける。時雄くんは「もうやっちゃったか。まだか、いやもうか」と悶々としっぱなし。
そのうちに田中くんが同志社を辞めて上京してくる。恋する二人は大盛り上がり。時雄くんは「監督者として」捨ててはおけないので、芳子さんの手紙を盗み読みしたりしてやっちゃったのかどうかを確かめようとする。でも分からない。別れる気配もない。それどころか家を出て、田中くんとふたり一生懸命に生きていきたいなどと言われてしまう。
で、「あんな駄目男と交際するなんて放ってはおけない」と、芳子さんのお父さんに時雄くん告げ口。お父さん上京。田中くんと三者面談。ここでも時雄くんは芳子さんのお父さんと「もうやっちゃいましたかねえ」「娘の態度を見ているとやっちゃったとしか思えませんな」「芳子さん、田中くんからの手紙を持ってきなさい」とやっちゃった証拠を捜そうと必死。芳子さんその場ではごまかそうとするけれど、翌日時雄くんに「実はやっちゃいました」と手紙で告白。時雄ブチキレ。お父さんに告げ口。芳子さん田舎に連れ帰られることに。時雄くん田中くんを訪問し「もうばれてるもんねー」と勝ち誇る。
芳子さんが帰ったあと、時雄くんは芳子さんのいた部屋に入り、蒲団の臭いを嗅ぎながら号泣したのだった。
というようなお話。とにかく重要なのは「やっちゃったかどうか」でまるでエロゲーのユーザーみたい。しかもやっちゃったと分かった途端「どうせ処女じゃねーんなら俺もやっとくんだった!」と後悔するのである。現代から見るとほぼ理解不能。恋愛を称揚しながらセックスは禁ずる当時の恋愛観も歪んでる気がするし、芳子さんが二言目には口にする「真面目な恋」というフレーズも寒い。これだけ分からないと言うことは逆にこの作品が民俗学的な資料としては有益*1なんだろうとは思うけど、今手に入る状態にしておく必要がどこにあるんだろ。
読みやすさだけが救いのような作品だった。
蒲団・重右衛門の最後 (新潮文庫)
田山 花袋 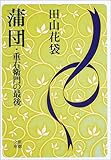
新潮社 1952-03-18
売り上げランキング : 128833
Amazonで詳しく見る by G-Toolsasin:4101079013